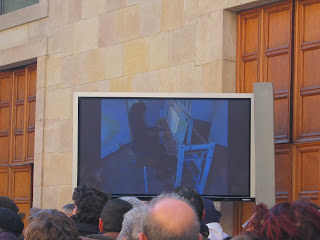|
| 左から:エラール(オリジナル)、フリッツ、ワルター2台 |
昨日は、Esmuc(カタルーニャ高等音楽院)で「フォルテピアノの日」が開催されました。一般公開で、申し込めば誰でも無料で参加できました。
フォルテピアノ科教授のArthur Schoonderwoerd氏による公開レッスン、友人の歌うミニコンサート、カンファレンス各種など盛りだくさんの、充実した一日でした。
ミニコンサートは、シュタイン(1792)モデルのフォルテピアノでC.P.E.バッハの歌曲と、フリッツ(1813)モデルの楽器でシューベルトの歌曲が演奏されました。たった50年しか違わない二人の作曲家の、とても異なる世界を垣間見ることができ、とても素敵な30分でした。
 |
| 公開レッスン |
2014-2015年にEsmucで新設されるフォルテピアノ入門コースに先立って、ピアニスト、ピアノの生徒、ピアノの教師・教員を対象に、フォルテピアノを知ってもらうのが目的でしたが、100人もの人が集まり、モダンピアノを含む計6台のフォルテピアノの音色を聴いて、触れることができたのは、素晴らしい企画だったと思います。
私にとっても大変有益で、楽しい一日となりました。いろいろヒントも得られました!バルセロナのフォルテピアノ製作家Paul Poletti氏のカンファレンスもとても面白かったです。